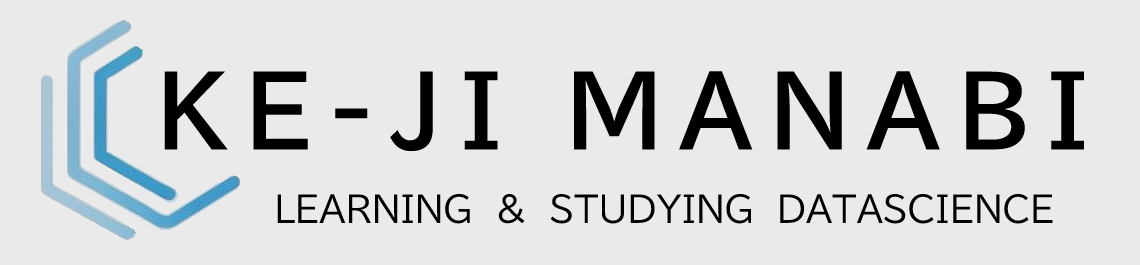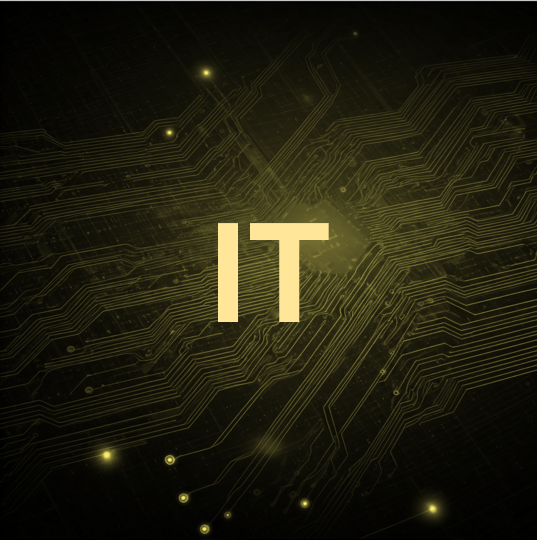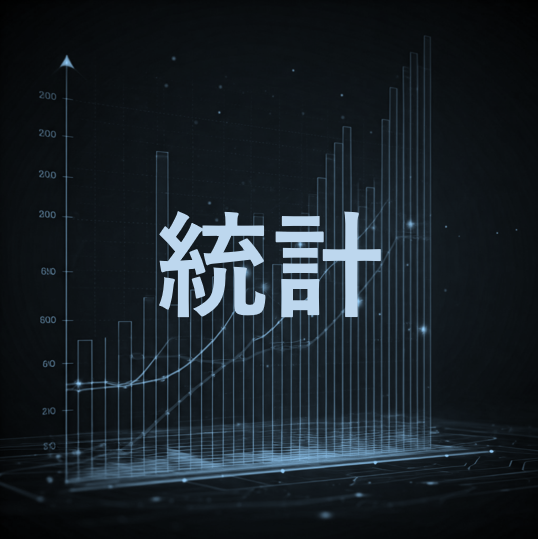こんにちは!けーじです。
私は2023年の1月からIT業界で働き始めているので、ちょうど丸3年働いたことになります。エンジニアに未経験で転職するって実際どうなのかといったところを綴ってみたいと思います。
ちなみに、去年も同じ時期に2年経過時の記事を書いていますので、興味があればそちらも覗いてみてください。
実際ITエンジニアの未経験転職ってどうなのか気になる方や、これから転職を考えている方の参考になれば幸いです。
転職した結果:総じて良かった
3年もすると未経験という扱いはほぼなくなってきていますが、その経歴に見合うだけのスキルを身に付けられているのかなと考えています。社内でも一定程度実力は認めていただけていると思います。入社当初はついていけなかったらどうしようかといった不安もありましたが、今ではあまりそのように感じることはなく、チームの技術レベルをどのように底上げすべきかなど、周囲を見渡しながら動ける範囲が広がってきたと感じています。
大変だったこと
うまくいっているとはいえ課題もあります。私はデータサイエンティストとして入社していまして、AIや統計といった知識を活用して業務に取り組んでいました。2023~2024年まではそのような案件で仕事をしていたりして、自分の知識を活用しながら業務に取り組めていたと思います。
求められる技術の変化
しかし、この1年でAIの仕事をすることの意味合いが大きく変わったように感じます。近年ベンダーから提供されるAIの成長が著しいです。そのためか良くも悪くも、自分たちでトレーニングしたモデルを使うよりも、大手ベンダーから出ているAIに対してAPIを利用するほうが効率的だと考えられるようになったと思います。モデルのトレーニングなどはほとんど行われなくなったのではと思います(私の周りだけかもしれないですが)。
その結果、AIを使用する人たちに求められるスキルに変化が見られるようになったと思います。個人的な感覚ですが、AI単体の知識だけでは不十分で、「AI + アプリ開発」や「AI + インフラ」といった掛け合わせのスキルが求められるシーンが増えました。LLMの台頭により、非エンジニアやユーザー側でも簡易的なPoC(概念実証)が可能になったからこそ、エンジニアには「その先の実装力や基盤構築力」が求められるようになったのだと感じています。
わからないのは仕方ない、キャッチアップが大切
もともとAIの知識で勝負しようとしていた私にとってはまずい流れでした。IT業界での経験が浅い私にとっては、常識レベルの知識も新たに勉強して身につける必要があります。実際にアプリ開発をする場面が発生しましたが、正直に自分のスキルについては説明して、多少の妥協を交えながらなんとか完成させた感じでした。
今では上記のこともありましたので、AIだけでなくアプリ開発の知識も体系的に学び直しています。アウトプットのためにもときどき記事にすると思いますので、もしよければご確認いただければと思います。(こういった勉強をしていくのも楽しいと思えるくらいにはエンジニアとしてうまくやれていると思います)
未経験でITエンジニアとして働くために必要なこと
最後に、実際に未経験でITエンジニアとして転職して働いてきた私から、独断と偏見を踏まえながら、未経験で転職するには何が必要そうかを書いてみます。
まず大前提として、数年前より未経験ITエンジニアの門戸は狭くなっているようです。YouTubeなどで見ることが多いのですが、例えばWEBエンジニアでは未経験でも求められる技術がどんどん上がっているようです。
要因としてはいくつかあるようですが、特に体感しているのはエンジニアの案件が減っているからではと考えています。ITエンジニアに振られたであろうタスクがAIに置き換わってきている(≒内製化)ことは予想ができますので、仕方のない流れではあると思います。
それでも未経験枠の採用は消失しているわけではないようです。業界全体として人手不足だというのは本当のようです。ただ、簡単なタスクしかこなせないエンジニアを雇うくらいなら、AIで代替してしまいたいという思いは変わらないと思います。つまるところ、「人手不足であることは間違いないが、採用基準自体は底上げされており、未経験であっても『即戦力に近いポテンシャル』が求められるフェーズ」に移行しているのだと思います。
未経験ITエンジニアに必要なスキル・経験など
ではどのような未経験ITエンジニアが採用されるのでしょうか?おそらく以下のようになると思います。よく言われていることかもしれないですが列挙してみます。
- アプリをデプロイしたことがある
- 資格を持っている
- 資格以外にコーディングなどの実績を示すなにかがある
- 最新技術をキャッチアップできる(特にAI関連)
- コミュニケーション能力
- 若い
アプリをデプロイしたことがあれば、評価としては高くなってくるのかなと思います。ただ、最近では単純なCRUDを実装しただけのアプリ(TODOアプリなど)はそこまで評価されないようです。AIとか絡めてオリジナルの機能を実装できると良いのかなと思ったりします。
資格やそれ以外の実績については、今後も自走して知識を身に着けられるかの証明になると思っています。ただ単に「独学で勉強しています」では、何もしていなくても言えてしまうため安心材料があると採用につながりやすいのだと思います。資格以外のものについては、GitHubのプロフィール欄であったり、私のようにブログがあればそれでも良いですし、競技プログラミングのレーティング、データサイエンティストであれば機械学習コンペ (Kaggleなど)の実績があると良いのかなと思います。(私が未経験で採用されたときは、統計検定やG検定、AtCoderのレーティングを評価していただいたようです。)
最新技術については、全エンジニアに必須の知識はAI関連でしょう。特にどのようなAIツールを用いているかは興味を持たれるのではないかと思います。最近では業務にAIを活用することが当たり前になっているので、そのようなツールが使えないといった状態では生産性が低いのでは?とみなされる可能性があります。その他、自身の業務に特化した最新技術をキャッチアップできていると高評価だと思います。
エンジニアに限った話ではないと思いますが、コミュニケーション能力は大事です。特に、IT技術について知見が浅い未経験エンジニアであれば最重要といっても過言ではないと思います。実際に案件に入って作業をする際に、技術がよくわからないのに質問もできないとなると、案件を回す立場からするとかなり扱いづらくなってしまいます。わからない部分は全力でキャッチアップするのは大前提ですが、聞いてしまえばすぐに解決することも多いので、コミュニケーション能力(特に質問)は常に意識しましょう。
後は若ければ若いほどよいと思います。未経験エンジニアであれば育成期間が考慮に入っていると思いますので、育成完了後長い期間成果を出してもらうためにはどうしても年齢を見ざるを得ません。(何歳まで、という具体的な数字は私にはよくわかりませんが、複数候補者がいるときにフィルタにかける要因にはなるだろうとは思ってます)
未経験スタートだけど今後もエンジニアとして成長していく
どうしても未経験でITエンジニアになると、周囲のエンジニアの方々との知識の差があります。分からないことは分からないとはっきり言って、質問する素直さが大事だと思います。そして知識が不足していると感じたら素早くキャッチアップする姿勢が求められます。地道に業務を積み重ねていけば知見がたまっていき、今度は自分が会社に恩返しできるほどのスキルを身につけられるでしょう(きっとそうでしょう、私も信じています⋯)。
以上、私の主観的な記述ばかりですが、どなたかの参考になれば幸いです。